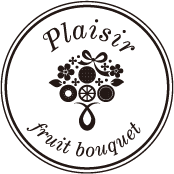「クラウンメロンが語る、“信頼”という価値」— トラブルの中で老舗が守った、贈り主の“顔”
「クラウンメロンが語る、“信頼”という価値」
— トラブルの中で老舗が守った、贈り主の“顔”
「メロンが届いたけど、匂いがどうもおかしかったらしくてね。
先方が千疋屋に連絡して、そこからすぐ連絡が来たのよ。」
ある日、母が語ってくれたエピソード。
役員が、お見舞いの贈答品として千疋屋にクラウンメロンを依頼したときのことだった。
届いた先で、状態に異変があった。
それを知った千疋屋は、すぐに贈り主へ連絡し、新しいメロンを再発送したという。
この話は、果物という“ナマモノ”を贈ることの難しさと、それでも選ばれ続ける老舗の本質を物語っていた。
“ナマモノ”を贈るというプレッシャー
フルーツは、どんなに選んでも、完璧にはいかない。
見た目も味も香りも、気候によって左右される。
“個体差”があり、“見えない品質”がある。
それでも、千疋屋や万惣が贈答フルーツの定番であり続けたのは、
「万が一のときに、贈る側の顔を守ってくれる」という信頼があったからだ。
贈答とは、単に渡すものではない。
自分の代わりに「想い」や「印象」を届ける行為。
その責任を、老舗は理解していた。
“クレーム対応”ではなく、“信頼対応”
今回のクラウンメロンの件で、千疋屋はこう動いた。
- 受け取った側から連絡が入る
- 内容を確認し、即座に贈り主に状況を共有
- 同日中に、新しいメロンを再手配
- 贈り主にも「対応済み」の安心を提供
これは、ただの“交換対応”ではない。
「贈った人が恥をかかないようにする」という視点に立った、“信頼の保全”だった。
受け取った側がクレームを言ってきたのではない。
むしろ、「このブランドから来たのに、珍しいね」という穏やかなトーンだった。
それでもすぐに対応した千疋屋の姿勢に、老舗のプライドと責任が垣間見える。
だから“千疋屋に任せる”が成立していた
「私たちがチェックするんじゃないの。千疋屋に頼むのは、そういうことだったのよ。」
母のその言葉に、贈答文化の本質が詰まっていると感じた。
“いいものを見極める”ことではなく、
“信頼できる相手に託す”——その判断に、贈り物を預かる人としての矜持がにじんでいた。。
たとえ高価でも、たとえ遠方でも、
「間違いないから」と胸を張って贈れる相手がいる。
それこそが、“贈り物を仕事として扱う人たち”にとって、何より重要なことだったのだ。
贈るとは、“信頼を届ける”ということ
このエピソードを通して、私は改めて実感した。
贈るという行為の本質は、「物を渡す」ことではない。
「相手との関係をどう結ぶか」を考える、信頼の文化そのものだということ。
果物はナマモノで、だからこそ難しい。
でも、そこに本当の気配りや誠実さが宿る。
プレジールも、そんな信頼に応えられるブランドでありたいと、心から思う。
▶ 次回予告:“皮が薄くなるまで”— 戦後世代が愛した果物”